
-
よい ゴール0120-410-506
- お問い合わせフォーム
よい ゴール0120-410-506
今回は、民事訴訟法における補助参加の利益の判断方法について説明させていただきます。
補助参加の利益についての説明をする前に、補助参加がどのような制度であるかを確認しておきます。
民事訴訟法42条は、「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。」としています。
このように、すでに裁判所に係属している訴訟に、当事者としてではなく、補助するために参加する場合を補助参加といいます。
補助参加をする人のことを参加人といいます。
参加人が補助をする当事者のことを被参加人といいます。
また、被参加人と訴訟をしている相手方当事者も登場することがあります。
補助参加の制度は、補助参加人が被参加人を勝訴させることにより自己(補助参加人)の法律上の利益を守るため、被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度です。
実際に、判例も同趣旨のことを述べています。例えば、最判昭和45年10月22日民集24巻11号1583頁は、「補助参加の制度は、他人間に係属する訴訟の結果について利害関係を有する第三者、すなわち、補助参加人がその訴訟の当事者の一方、すなわち、被参加人を勝訴させることにより自己の利益を守るため、被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度」であるとしています。
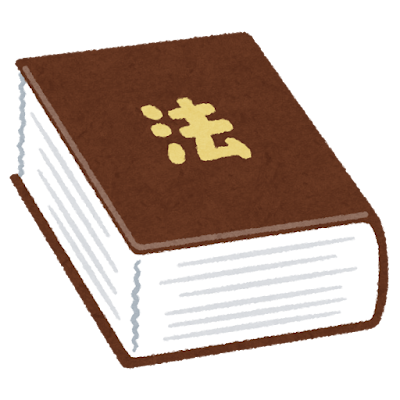
参加人が補助参加をする場合において、当事者が異議を述べたときは、裁判所が補助参加を認めるか否かについての判断をします(民事訴訟法44条)。その際に、裁判所は、補助参加をしようとしている者が「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」であるか否かを判断します。
それでは、訴訟の結果について利害関係を有する第三者」であるかはいかなる基準で判断されるのでしょうか。この考え方について説明していきます。
訴訟の結果が何を意味するのかについては学説上争いがあります。
まず、1つ目の立場が訴訟物限定説の立場です。
この立場は、訴訟の結果を訴訟の勝敗と考えます。そして、民事訴訟が訴訟物たる権利関係の存否について判断をするものである以上、訴訟の勝敗とは、裁判所がした訴訟物たる権利関係の存否についての判断になります。
この立場によると、判決理由中の判断について利害関係を有する第三者には参加が認められないことになります。
これに対して、判決理由中の判断について利害関係を有する第三者にも参加を認める立場があります。それが、訴訟物非限定説の立場です。
この立場は、訴訟の結果を、訴訟物たる権利関係が認められるか否かについての判断の理由と考える立場だといえるでしょう。
次に、利害関係の意味について説明していきます。
この利害関係とは、判例の立場によるならば、訴訟の結果について法律上の利害関係を有する場合を意味すると考えられています。
例えば、最判昭和39年1月23日集民71号271頁は、補助参加が認められるのは、専ら訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られると判断しています。
そのように考えられる理由は、補助参加の制度が、参加人が被参加人を勝訴させることにより自己(補助参加人)の法律上の利益を守るため、被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度だからです。
この立場によると、例えば、友人を助けたいという気持ちがある人や経済的利害関係を有するという人が参加することは認められないことになります。
以上のような立場にたったときに、法律上の利害関係とはどのような意味かを確定する必要があります。
この点について、最高裁は次のように定義しています。
法律上の利害関係を有する場合とは、「当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合」を意味する(最判平成13年1月30日民集55巻1号30頁参照)。
最高裁は、「法律上の利害」についての関係のことを「当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益」について影響を及ぼすおそれがある場合と定義しています。したがって、影響のことを法律上の影響がある場合だと言っているわけではないことになります。
訴訟の判決が影響を及ぼす場合は、2種類あります。
まず、訴訟法上の影響が与えられる場合です。訴訟法上の影響とは、例えば、既判力があげられます(民事訴訟法114条1項)。ただし、既判力が拡張されるような場合には、類似必要的共同訴訟にあたることから、共同訴訟参加を利用することもできます(民事訴訟法52条)。
次に、事実上の影響がある場合です。これは、裁判所の判決を別の裁判所が事実上参考にすることを意味します。
ある裁判所の判断を参加人が他人から請求を受けたりする可能性がありますが、これは事実上のものにすぎません。
このような場合を主眼として、補助参加の制度は設けられているといえるでしょう。

以上から、補助参加の利益は、当該訴訟の結果が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に事実上影響を及ぼすおそれがある場合に認められるものといえるでしょう。
具体的な事案において、補助参加を検討している方や補助参加に対して異議を出したいと考えている方は、弁護士までお問い合わせください。
