
-
よい ゴール0120-410-506
- お問い合わせフォーム
よい ゴール0120-410-506
この記事では、「所有権に基づく不動産明渡請求訴訟の請求の趣旨と訴訟物について」に続き、所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権の要件事実を、具体的なケースを用いて解説します。
土地の不法占有が発覚した際、所有者はどのような要件のもとで土地の返還(明渡し)を請求できるのか。不動産明渡訴訟における主張立証の実務的ポイントを把握することで、スムーズかつ的確な権利行使が可能となります。
以下のような典型事例を前提に考えていきましょう。
〔事例〕
Xは甲土地を所有している。ある日、Xが現地を訪れたところ、第三者Yが土地を占有していたため、明渡請求訴訟を提起した。
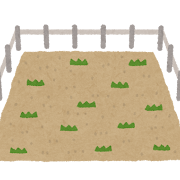
〔訴訟内の展開〕
Yは、Xの所有権自体は認めつつも、「甲土地は月額3万円で借りていた」と主張。したがって、土地占有について正当な権限があるとして、返還義務を否定した。
このような訴訟では、明渡請求が認められるために、いかなる法的要件を主張・立証すべきかが争点となります。
所有権に基づく返還請求権が認められるためには、以下の3つの事実が必要です。
・①原告が対象土地の所有権を有していること
・②被告がその土地を現在占有していること
・③被告に正当な占有権限が存在しないこと
①②は所有者であれば比較的立証しやすいのに対し、③(被告が無権限であること)は慎重な検討を要します。
この3要件のうち、①②については当然に原告が主張・立証責任を負います。では③についてはどうでしょうか。
民法188条により、占有者の権原は「適法に推定」されます。しかし、これをそのまま適用すれば、原告が被告の「無権限性」まで立証しなければならず、不法占有者の排除が困難になります。
そこで判例(最判昭和35年3月1日)は、返還請求権行使において民法188条の推定は適用されないと判断。つまり、正当な権原があることは被告側の抗弁事実であり、その立証責任は被告にあると整理されています。
この考え方は、実務上も通説として受け入れられており、不動産明渡訴訟の基本的構造として重要な意味を持ちます。

・Xが甲土地の所有者であること
・Yが甲土地を占有していること
上記2点は、請求原因事実として原告側が記載すべき事項です。今回のケースでは、YもXの所有権や自らの占有を否定していないため、争点化していません。
・XとYの間で、甲土地を賃料月額3万円で貸し渡す契約が存在したこと
・Yがその契約に基づいて占有していること
この主張は、正当な占有権原の存在を前提とする抗弁であり、立証責任は被告にあります。
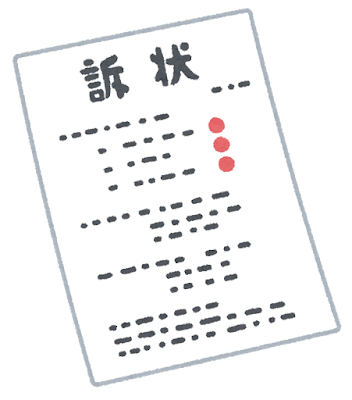
第1 請求原因事実
1 Xは、甲土地を所有している。
2 Yは、甲土地を占有している。
第2 認否
請求原因事実1、2については認める。
第3 抗弁事実(賃貸借契約)
1 Xは、Yに対して甲土地を3万円で賃貸した。
2 Yは、上記契約に基づいて甲土地の引渡しを受けた。
第4 抗弁に対する認否
抗弁事実1および2は否認する。
所有権に基づく土地明渡請求は、シンプルな構造に見える一方で、主張・立証責任の配分を適切に理解しなければ、訴訟戦略を誤るおそれがあります。特に、相手方が「口約束の賃貸借契約」などを主張するケースでは、抗弁としての適否や証拠の存否を精査することが極めて重要です。
本記事は一般的な構造と事例に基づいて説明していますが、個別事案によっては異なる主張整理が必要となる場合もあります。不動産トラブルや占有に関するお悩みがある方は、お早めに法律専門家までご相談ください。
なお、「賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求訴訟」の記事では、契約終了を理由とした明渡請求について詳しく解説していますので、併せてご参照ください。