
-
よい ゴール0120-410-506
- お問い合わせフォーム
よい ゴール0120-410-506
今回は、将来給付の訴えの利益について、その有無の判断方法を示した大阪国際空港事件(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)を用いながら紹介させていただきます。
→ 関連記事:訴訟手続の基礎については「冒頭手続とは何か」もご参照ください。

大阪国際空港周辺の住民Xらは、同空港の設置・管理の主体である国Yに対して、夜間の航空機の発着の差止めを求めるとともに、それにより過去に生じた損害に加え、将来生じる損害も含めて賠償を求める訴えを提起しました。
Xらが損害賠償を求める部分のうち、将来生じる損害の賠償を求める部分について、訴えの利益が認められるのか。
→ 関連記事:不法行為に基づく責任については「従業員が車で事故を起こしたときに会社は責任を負いますか」や「使用者責任について」も合わせてご覧ください。
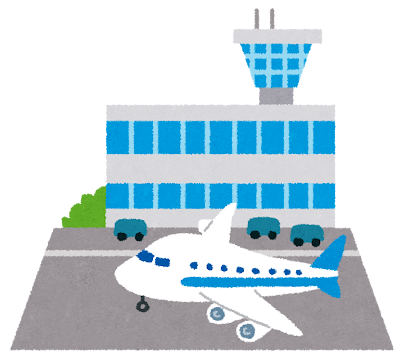
民事訴訟法135条は、将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができるとしています。
しかし、今回紹介している判例においては、同条は、どのような請求権でも「あらかじめその請求をする必要がある場合」にあたれば将来給付の訴えの利益を認めるという趣旨ではなく、将来給付の訴えの利益が認められる請求権は一定の要件(資格)を充たしている必要があると考えています。
そして、「既に権利発生の基礎をなす事実上及び法律上の関係が存在し、ただ、これに基づく具体的な給付義務の成立が将来における一定の時期の到来や債権者において立証を必要としないか又は容易に立証しうる別の一定の事実の発生にかかつているにすぎず、将来具体的な給付義務が成立したときに改めて訴訟により右請求権成立のすべての要件の存在を立証することを必要としないと考えられるようなもの」が将来給付の訴えの利益が例外的に認められる場合だと考えています。
→ 関連記事:条文の解釈に関連するテーマは「文書提出命令が発令される要件について」でも解説しています。
今回の判例の事案は、飛行機の離発着という継続して行われる不法行為により原告が損害を被ったという事案です。このような継続的不法行為に基づき将来発生すべき損害賠償請求権について、将来給付の訴えの利益が認められる請求権の資格が認められる場合はどのような場合でしょうか。
判例は、次のように述べています。
「右請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測されるとともに、右請求権の成否及びその内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来における事情の変動としては、債務者による占有の廃止、新たな占有権原の取得等のあらかじめ明確に予測しうる事由に限られ、しかもこれについては請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止しうるという負担を債務者に課しても格別不当とはいえない点において前記の期限付債権等と同視しうるような場合には、これにつき将来の給付の訴えを許しても格別支障があるとはいえない。」
このような判例の文言を踏まえると、将来給付の訴えの利益が認められる請求権としての適格は、3つの要件を充たした場合に認められると考えられます。
①右請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測されること
②右請求権の成否及びその内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来における事情の変動としては、債務者による占有の廃止、新たな占有権原の取得等のあらかじめ明確に予測しうる事由に限られること
③②の事由については請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止しうるという負担を債務者に課しても格別不当とはいえない点において前記の期限付債権等と同視しうるような場合であること
以上の3つの要件を充たすことによって、はじめて請求権としての適格が認められることになります。そして、この請求権としての適格を充たしたときに、はじめて、「あらかじめその請求をする必要がある場合」に当たるか否かを判断することになります。
→ 関連記事:「補助参加における参加の利益」もあわせて読むと理解が深まります。
将来給付の訴えは、将来の権利または法律関係に関する主張の当否を判断する訴えです。将来の権利または法律関係は、現在、すなわち、口頭弁論終結時点において発生するか不確定な権利です。
そのような権利を発生するものとして、判決効や既判力、執行力を生じさせると、判決後、将来に権利が発生しなかったとしても、債務名義があることから執行を開始できてしまいます。
債務名義があると、実体法上の権利があることを前提にして、その後の強制執行が行われることになります。そうすると、被告は、権利が消滅した事情について、自ら主張して、請求異議の訴えを提起する必要があります。この場面において、請求異議の訴えが認容されるためには、被告自ら権利の消滅という自分にとって有利な事情を主張立証する必要があります。
この事情が予測不可能となってしまうと、被告の負担も増えてしまうことは明らかでしょう。そこで、②と③の要件が要求されることになっています。
→ 関連記事:裁判における当事者の負担に関連して「裁判上の自白について」も参考になります。

今回は、将来給付の訴えの利益が認められる場合について判断した大阪国際空港事件の判例を紹介させていただきました。
事案によっては、将来給付の訴えが認められる場合もあります。具体的な事案について将来給付の請求を行えるかについては、弁護士までお問い合わせください。
→ 関連記事:和解や訴訟解決の場面については「和解とはどのような契約ですか」「和解にはどんな事項が書かれているか」もご確認ください。
