
-
よい ゴール0120-410-506
- お問い合わせフォーム
よい ゴール0120-410-506
今回は、動産の物権変動の対抗要件について紹介させていただきます。
⇒ 関連記事:保証契約について
物権変動とは、物権を得たり、失ったり、物権の内容を変更したりすることを意味しています。例えば、所有権を得たり、失ったりすることが具体例としてあげられます。
動産とは、不動産以外の有体物のことを意味しています。例えば、絵画や機械などがあげられます。
民法上、動産の物権変動の対抗要件についてはどのような規律がされているでしょうか。この点について以下で解説していきます。

動産の物権変動には、相続や譲渡があります。このうち、譲渡については、対抗要件についての規定が設けられています。
民法178条がその規定にあたります。同条は、次のように定めています。
「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」
不動産の物権変動についての対抗要件について定めているのが、民法177条です。同条は、不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができないと定めています。
これら隣り合う2つの条文を比較すると、次のことがわかります。
①動産では、不動産の場合と異なり、物権の譲渡だけが対象になっています。
②動産の場合には、「登記」ではなく「その動産の引渡し」が対抗要件です。
③「第三者」の意義は不動産の場合と同じです。
⇒ 関連記事:所有権に基づく不動産明渡請求訴訟の請求の趣旨と訴訟物について
ここで、動産の意味について確認しておきます。
民法85条は、民法上の物を有体物であるとしています。そして、民法86条1項は、土地及びその定着物、例えば建物は不動産とするとしています。そして、同条2項で、不動産以外の物をすべて動産としています。
そうすると、自動車は不動産ではないことから、動産であることになります。同じように、絵画も不動産でないことから、動産であるとわかります。
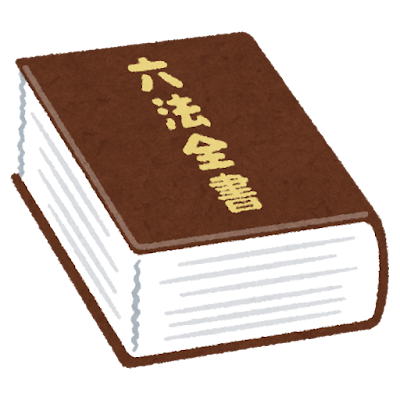
⇒関連記事:専有部分と共用部分の区別
上述のように、動産の物権の譲渡に関する規律においては、対象となる物権は、所有権に限定されています。また、動産の所有権を取得する原因となる行為(所有権取得原因)のうち譲渡だけだと考えられています。
これは、動産を売却した契約を解除したときの所有権の回復も譲渡と同視されることから、譲渡だけでよいと考えていることの現れだといえるでしょう。
⇒関連記事:賃貸人の第三者に対する返還請求について
引渡しとは、占有の移転を意味しています。現実に占有が移転する場合、たとえば、絵画を直接手渡しする場合だけでなく、4つの引渡しの方法が定められています。現実の引渡しだけに絞ってしまうと、引渡しを行うために、一度動産を取り戻して、再度返すという面倒な手順をふまなければならなくなってしまうからです。
4つの引渡しの方法とは、
現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転
です。
以下では、それぞれの詳細について解説します。
民法182条1項は、「占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする」としています。これを現実の引渡しといいます。
具体例としては、売却した絵画を相手に手渡しすることがあげられます。
民法182条2項は、「譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。」としています。これを簡易の引渡しといいます。
例えば、Aは、自己が所有している絵画をBに売却した。その絵画は、売却前にBに貸し出していたことからBの手元にあったという事例において、AがBから絵画を取戻し、その後現実の引渡しをするのは面倒です。そこで、法は、AがBに対して意思表示をするだけで引渡しが完了するようにしました。
民法183条は、代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得するとしています。これを占有改定と言います。
Aは、自己が所有している絵画をBに売却した。Aは、その絵画を売却後も自己の手元に置いておきたかったという事例において、Aは自分の絵画を手元に置いたままBに所有権を譲渡するという取引を行いたいと考えることもあります。
外部から見て所有権の移転は明確とはいえません。Cからみると、Aが真の所有権者であるのか、それとも所有権が移転したがAが誰かのために占有しているのか、わからないことになります。
絵画を購入したいCは、Aに対して所有権が残っているかを確認することになります。Aが譲渡したにもかかわらず、さらに売却して利益を得るためにうそをつく可能性もあることから、公示の機能としては不十分であるという批判もあります。
しかし、取引上の便宜を図る必要があること、第三者(この事例ではC)を保護するためには即時取得の制度を利用すれば十分であることから民法178条にいう引渡しの中に、占有改定を含める立場が判例・通説の立場です。
例えば、明治時代の判例も占有改定も引渡しに含めています(大判明治43年2月25日民録16輯153頁)。
なお、判例によると、「代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する」ことについて、代理人と本人の合意が必要です(大判大正4年9月29日民録21輯1532頁)。
民法184条は、代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得すると定めています。これを指図による占有移転といいます。
例えば、Aは、自己が所有している絵画をBに売却した。その絵画はAがCに預けていたという事例では、代理人はCで、本人はAで、第三者がBになります。
指図による占有移転を行うためには、AはCに対して「以後Bのために絵画を占有してください」と命じる必要があります。これが指図にあたります。
そして、代理人CではなくBの承諾が必要になります。
⇒関連記事:敷金はいつ返ってくる?返還される条件と請求方法を弁護士が解説
以上のように、民法178条にいう動産の引渡しには、4つの類型があります。
動産の引渡しを求める訴訟ではこれらの事実を主張することもあります。
また、特別に対抗要件の具備の方法が規律されている場合もあります。
具体的な事案においてどのような事実を主張すべきかについてお困りの方は弁護士までお問い合わせください。
