
-
よい ゴール0120-410-506
- お問い合わせフォーム
よい ゴール0120-410-506
今回は、売買契約を締結したにもかかわらず、その目的物を引渡してもらえないというときに、どのような請求をすることができるか、その訴状に請求原因事実としてどのような事実を記載する必要があるかについて、具体的な事例を用いながら解説していきます。
※保証契約の成立要件については、関連記事「保証契約について」も参照してください。
Xは、2024年2月1日に、Yから、甲土地を700万円で購入した(以下、「本件売買契約」という。)。しかし、Yは甲土地を引渡そうとしてくれません。また、登記の移転も完了していません。そこで、Xは、Yに対して、甲土地の引渡しと登記の移転を求めたいと考えています。具体的に、XはYに対してどのような請求をすることができるでしょうか。また、その際には、どのような事実を記載すればよいのでしょうか。
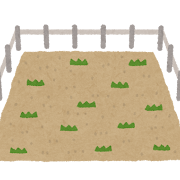
Xは、Yに対して本件売買契約に基づいて、甲土地の引渡しと登記の移転を求めています。
登記をする際には、登記原因についても示す必要があります。そこで、XはYに対して、売買を原因とする登記の移転を求めることになります。
以上から、請求の趣旨は、以下のようになります。
※不動産訴訟の請求構成については、「所有権に基づく不動産明渡請求訴訟の請求の趣旨と訴訟物について」もあわせて参考になります。
Yは、Xに対し、甲土地を引渡せ。
Yは、Xに対し、甲土地について2024年2月1日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。

売買は、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法555条)。
したがって、売買契約が成立すると、売主は、買主に対して、財産権を移転するという義務を負うことになります。これを買主(債権者)の立場からみると、買主は、売主に対して、売買契約に基づく財産権移転請求権を有しています。
具体的には、買主であるXは、売主であるYに対して、本件売買契約の目的物である甲土地の引渡しを求めています。
以上から、訴訟物は、売買契約に基づく財産権移転請求権としての土地引渡請求権になります。
また、売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負います(民法560条)。甲土地の対抗要件である登記を備えさせる義務も売主Yの負う財産権移転義務の内容に含まれます。
対抗要件を備えさせる義務と財産権を移転する義務は共に同じ売買契約から生じる1個の財産権移転請求権に対応する1個の義務になります。そこで、訴訟物は売買契約に基づく財産権移転請求権の1個だといえます。
以上から、事例においてXがYに対して行う請求における訴訟物は売買契約に基づく財産権移転請求権としての土地引渡請求権及び所有権移転登記請求権、1個になります。
※不動産の引渡請求に関しては、「賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求訴訟」との比較も有益です。
さて、XはYに対してどのような事実を主張して、財産権の移転を請求すればよいのでしょうか。
ここで、冒頭規定説の考え方を紹介します。
冒頭規定説の考え方を一言で表せば、民法に書かれている契約の効力は、その民法の契約の冒頭規定に書かれている要件に該当する具体的な事実がある場合に発生するものである。
例えば、売買契約の冒頭規定は、民法555条です。その規定の内容は、「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」というものになります。
このような規定を踏まえると、売主がある財産権を買主に移転することを約し、買主がこれに対してその代金を支払うことを約することによって売買契約の効力が発生し、当該契約の履行請求をすることができることになります。
この考え方は、ある権利の発生の根拠を法律により生じると考える立場(法規説)を根拠としています。これに対し、当事者の合意から生じると考える立場もあります(合意説)。
法律の規定なしに法律効果が生じると考えることはできません。そこで、法規説を採用するというのが判例・通説です。
この立場によるならば、法律の規定により契約の拘束力が発生し、原告の被告に対する権利が生じることになります。また、合意の法的性質を認識させるような事実(例えば、売買に当たるか、賃貸借に当たるかなど)を主張立証する必要はないことになります。したがって、単に、「目的物を引き渡すことを合意した」と主張すればいいことになります。
以上のように、原告は、自ら選択した契約の成立要件に該当する具体的な事実を主張する必要があり、かつ、それで足ります。
そして、民法上第2節から第14節まで定められた契約、すなわち、典型契約は、その冒頭にある規定が当該契約類型の成立要件を規定していると考えられます(冒頭規定説)。そこで、冒頭規定に書かれた要件に該当する具体的な事実を主張する必要があります。
この考え方に従うと、冒頭規定が定めていないもの、例えば、期限・条件などは、権利の発生を障害・消滅・阻止するものとして、抗弁になります。
そこで、これらの事情がある場合には抗弁として被告が主張立証責任を負うことになります。
以上から、Xは訴状に請求原因事実として、以下の事実を記載する必要があります。
Xは、2024年2月1日に、Yから、甲土地を700万円で購入した(以下、「本件売買契約」という。)。
よって、Xは、本件売買契約に基づいて、Yに対し、甲土地の引渡し及び2024年2月1日売買を原因とする所有権移転登記手続を求める。

以上のように、売買契約の買主は、目的物の引渡し並びに登記をするように求めることができます。これに対して、売主側の抗弁が認められなければ、買主の請求は認められることになります。
なお、具体的な事案についてどのような対応がとれるかの詳細につきましては、弁護士までお問い合わせください。
※訴訟後の解決方法として「和解とはどのような契約ですか」もあわせてご覧ください。
