
-
よい ゴール0120-410-506
- お問い合わせフォーム
よい ゴール0120-410-506
今回は、譲渡担保の法律構成について解説していきます。なお、今回は、所有権的構成の考え方と担保的構成の考え方の違いを理解するためのツールとして、次のような事例を用います。
[事例]Aは、Bに対して負う債務を担保するために、Bに甲絵画を担保として譲渡した。
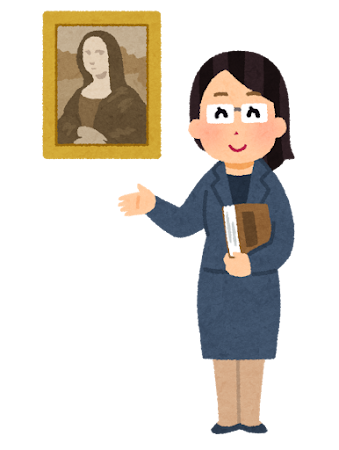
●関連記事
所有権に基づく不動産明渡請求訴訟の請求の趣旨と訴訟物について
譲渡担保権の法的性質については、大別して所有権的構成と担保的構成の2つがあると言われています。そこで、今回は、これらの考え方の違いがどうなっているか、最高裁はどのように判断しているかについて検討していきたいと思います。
所有権的構成とは、譲渡担保権の設定により目的物の所有権が担保権者に移転するという立場のことです。譲渡担保権設定契約により目的物の所有権が移転したという法的関係、すなわち、形式を重視している立場といえます。
それでは、所有権的構成によると、[事例]はどのような法律関係になるのでしょうか。
所有権的構成を前提とすると、動産譲渡担保権の設定契約により、譲渡担保設定者Aから譲渡担保権者Bに所有権が移転したと考えることになります。そうすると、被担保債権であるBのAに対する債権が債務不履行となる前に、Bが第三者Cに甲絵画を売却した場合であったとしても、Cは甲絵画の円満な所有権を取得することになります。そして、Cが対抗要件を具備した場合には、AはCに対して自己の所有権を主張することができないという結論になります。
また、[事例]において、倒産が発生した場合にも2つの考え方により違いが生じることから解説していきます。
所有権が移転したという形式を重視すると、譲渡担保権は取戻権(破産法62条など)の基礎となるという帰結がもたらされることになります。
例えば、事例において、譲渡担保設定契約後に譲渡担保設定者Aが破産したという場合には、Bが甲絵画に対して所有権を有していることになるから、取戻権を行使して、甲絵画の引渡しを求めることができることになるはずです。
● 関連記事
担保的構成の考え方は、所有権の移転が譲渡担保権の設定の譲渡担保権者には移転しないという立場です。
譲渡担保設定契約により譲渡担保権者に目的物の所有権が移転するか否か、譲渡担保設定者にいかなる権利が帰属するかについては担保的構成の内部においても対立があります。
例えば、譲渡担保設定契約により譲渡担保権者に債権担保の目的の限度において目的物の所有権は移転し、残りは「設定者留保権」という物権が譲渡担保設定者に帰属していると考える立場があります。
この立場は、譲渡担保権設定契約時点において、譲渡担保権者が担保の目的物の経済的価値のみを把握していることを重視する立場であるといえるでしょう。
担保的構成の帰結を考えるために、上記で用いた事例を用いて説明します。
この場合において、Bが債務不履行前に第三者Cに甲土地を売却してしまったとしても、AはCに対して自己の設定者留保権を主張できることになります。そして、即時取得の要件を充たさなければ(民法192条)、Cは円満な所有権を取得できないことになります。
また、倒産の場面においても、所有権の移転という形式よりも抵当権などの経済的価値を把握する担保権として捉えるべきであることから、取戻権ではなく別除権(破産法2条9項・同法65条など)として取り扱うべきことになります。そうすると、民事再生法の場面においては、担保権消滅請求の対象になったりするなど、倒産の場面において権利行使が取戻権の場合と比較して制限される可能性があることになります。
●関連記事
文書提出命令が発令される要件について | 弁護士法人リコネス法律事務所
民事訴訟の場面において証拠となる文書はどのように提出しますか
判例には、担保的構成に親和的な判例が存在します。例えば、会社更生の場面において、譲渡担保権者を更生担保権者として取り扱うべきだと判断した判例(以下、「昭和41年判例」とする。)があります。
所有権的構成の立場によるならば、昭和41年判例のような会社更生の事例では、取戻権として取り扱うべきだと主張すべきことになります。これに対し、同判例は、抵当権者をはじめとする他の典型担保を有する者と同様に、譲渡担保権者を更生担保権者として取り扱うべきだとしています。以上を踏まえると、昭和41年判例の立場は、担保権的構成に親和的なものと言えます。
一方で、最判昭和62年11月10日民集41巻8号1559頁(以下、「昭和62年決定」という。)において、最高裁は、譲渡担保権者が民法333条にいう第三取得者に当たると判示しています。
民法333条にいう第三取得者は、公示の方法がない動産売買先取特権の目的物を取得した第三者を保護することによって、動産取引の安全を図るために設けられた規定です。
このような趣旨を踏まえると、第三取得者は、動産売買先取特権の目的物の所有権を取得した者を指し、それ以外の占有取得者を含まないことになるはずです。
譲渡担保権の法的性質を所有権的構成により説明するならば、民法333条の適用は肯定されるべきです。他方で、担保権的構成により説明するならば、質権の設定により動産の占有を取得した者と動産売買先取特権者との間の優劣関係について定めた民法334条の類推適用を主張する方が適切であるはずです。
以上の検討を踏まえると、昭和62年決定は、民法333条を適用すべきであると判示している点で、所有権的構成に親和的な判断だといえるように思います。
しかし、本件の調査官解説によると、担保権的構成の立場に立ったとしても、民法333条の第三取得者については譲渡担保権者も含まれるという考え方は採用できることを前提にして判断をした旨を述べています。このような「非競合説」を採用したものであることを踏まえると、担保権的構成を採用したものだと捉えることもできます。

●関連記事
以上のように、最高裁は、譲渡担保の法律構成について、所有権的構成とも担保権的構成ともとることができる判断をさまざま提出しています。
具体的な事案において、譲渡担保権についてどのような主張をすべきかについてお困りの方は弁護士までお問い合わせください。

● 関連記事