
-
よい ゴール0120-410-506
- お問い合わせフォーム
よい ゴール0120-410-506
訴訟上の場面だけでなく、訴訟外の場面でも、和解がなされることは多くあります。
弁護士が関与する場合には、後の紛争を回避するために、書面で合意をすることが多いです。今回のコラムでは、和解条項の中では、どのような事項が記載されているかについて、その内容を、具体的な記載例を踏まえながら解説していきます。

和解契約とは、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる契約です(民法696条)。和解契約における争いとは、法律関係に関する争いです。そして、後日再び争いをすることを防ぐためには、どのような法律関係に関する争いであるかを確定する必要があります。このような場面で用いられているのが、確認条項です。
確認条項とは、特定の権利や法律関係の存在や不存在を確認する条項のことです。
確認条項の例としては、次のようなものが考えられます。
被告は、原告に対し、令和7年4月1日付けの原告と被告との間の売買契約に基づく代金支払債務として100万円の支払義務があることを認める。
確認条項に必須の要素は、①当事者、②確認対象となる権利関係、③確認文言です。
①当事者とは、誰と誰との間での確認であるかを意味しています。
今回の記載例だと、原告と被告になります。
②確認対象となる権利関係とは、訴訟上の和解においては、訴訟物となっている権利又は法律関係を意味しています。
例えば、記載例における確認対象は、令和7年4月1日付けの原告と被告との間の売買契約に基づく代金支払債務、すなわち、原告の被告に対する売買契約に基づく代金支払請求権になります。
③確認文言は、今回の記載例では、「認める。」という部分のことです。このように記載することにより、後述するような、給付条項や形成条項といった他の条項と区別して、確認条項であることを示すことができるようになります。

2でみてきたような代金支払債務が認められたとしても、そのような権利を実際に実行できなければ意味がありません。
もしも、買主が代金の支払いに応じないときには、裁判所に申立てをして、強制執行をすることになります。強制執行をするためには、債務名義とよばれる権利の存在を裏付ける文書が必要になります。その文書に、具体的な給付内容が記載されていることではじめて強制執行を行うことができます。このような給付に関する条項のことを給付条項といいます。
給付条項とは、当事者の一方が、相手方に対して一定の給付をすることを内容とする条項のことです。
給付条項の例としては、次のようなものが考えられます。
被告は、原告に対し、100万円を、令和7年5月1日限り、債権者名義の〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座(口座番号〇〇〇〇)に振り込んで支払う。
給付条項に必須の構成要素は、①当事者、②目的物、③給付約束文言です。
上記の記載例をもとにして、①から③の解説をします。
①は、確認条項のときとほとんどかわりません。
②については、今回は、100万円です。目的物は、土地建物であったり、絵画であったりすることもあります。
③については、「支払う」という部分にあらわれています。「支払う」という文言があってはじめて、裁判所は強制執行をすることができるようになります。この記載が確認条項のような記載であると強制執行はできません。
また、③令和7年5月1日限り、④債権者名義の〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座(口座番号〇〇〇〇)に振り込んでという部分は、支払の日時や方法に関する特約に相当する部分です。このように、支払期限、支払場所や支払方法を定めることも当然できます。
記載例でいえば、③は、支払期限、④は、支払方法に関する記載だといえるでしょう。
他にも、分割払いの定めがされたり、先に土地を引き渡すといった条件を付加する定めがなされたりすることもあります。
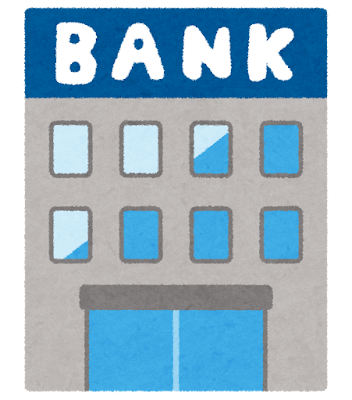
形成条項とは、当事者が自由に処分することができる権利又は法律関係について、新たな権利の発生、変更、消滅の効果を生じる合意を内容とする条項のことです。
例えば、賃貸借契約において、賃料を変更する合意をすることなどがこれに当たります。
清算条項とは、訴訟の対象となっている権利関係やそれ以外の権利関係について、和解条項の中に含まれていない法律関係を清算する趣旨の条項のことです。
例えば、売買契約に基づく代金支払請求とともに遅延損害金の支払を求めている場合に、遅延損害金の請求はしないこととする合意をした場合には、「原告はその余の請求を放棄する。」というような権利放棄条項が設けられることがあります。
また「原告と被告は、原告と被告との間には、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。」という包括的清算条項が設けられることもあります。
他には、訴訟事件において、訴訟費用に関する条項や、関連する保全事件の取下げに関する同意等の関連事件の処理条項等が設けられること等もあります。
以上でみてきたように、和解条項の中では、さまざまな条項が設けられます。そして、それらは、事件を解決し、その後の執行に備えたものになります。
具体的な事件における和解条項がどのような意味をもっているかについては、弁護士までお尋ねください。
