
-
よい ゴール0120-410-506
- お問い合わせフォーム
よい ゴール0120-410-506
今回は、予備的併合がなされている場合に、控訴審がどのような判決をすることができるかについて解説していきます。その説明のために、今回は、以下の事例を用います。
Xは、Yとの間で売買契約を締結したが、代金を支払ってくれない。そこで、Xは、Yに対して、売買代金支払請求訴訟を提起した。その際に、売買契約が無効と判断された場合に備えて、予備的に不当利得返還請求を行った。
第1審裁判所は、売買契約が無効だと判断して、主位的請求である売買代金支払請求を棄却する判決をするとともに、予備的請求である不当利得返還請求を認容する判決をした。
原告は控訴も附帯控訴もしておらず、この判決を不服としたYのみが控訴した。
控訴審は、第1審と異なり、売買契約が有効だという心証に達した。控訴審裁判所はどのような判決をすべきか。
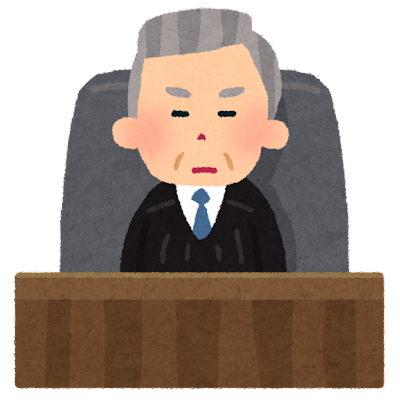
この訴訟において、Xの主張している訴訟物は2個あります。売買契約に基づく代金支払請求権と不当利得返還請求権です。これら2つの訴訟物は、実体法上両立しない関係にあります。なぜならば、同じ売買契約が有効であり、かつ、無効であるということはありえないから、売買代金請求権と不当利得返還請求権は実体法上両立しない関係にあるといえるからです。
このような実体法上両立しない関係に当たる2つの訴訟物の併合形態は、予備的併合に当たります。予備的併合とは、主位的請求について無条件に審判を求め、予備的請求については、前者の認容を解除条件として審判を申立てる併合形態のことです。
まず、2つの請求について、移審効と確定遮断効がどのように生じているかを確認します。
上訴不可分の原則により、すべての請求に対して、確定遮断効と移審効が生じています。したがって、控訴審に売買代金請求権と不当利得返還請求権の両方の請求が移審していることになります。
当事者の申立てと裁判所の判決を比較して、前者が後者よりも小さいときには不服の利益が認められるとする形式的不服説の立場にたつと次のような結論になります。
被告が第1審で求めていた申立事項は、主位的請求も予備的請求も請求棄却判決です。一方で、裁判所の判決は、主位的請求は棄却だが、予備的請求は請求認容判決になります。被告の申立て事項と判決事項を形式的に比較すると、裁判所の判断の方は被告の申立てよりも少ないです。したがって、被告に控訴の利益は認められます。
※控訴の利益や当事者の手続的地位について詳しく知りたい方は、関連記事「補助参加における参加の利益」も参考になります。

控訴審では、移審した請求のうち、「当事者が第一審の判決の変更を求める限度において」審理が行われます(民訴296条1項)。そして、控訴審裁判所による第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすること(民訴304条)ができます(不利益変更禁止の原則)。
控訴人であるYの立場からみれば、原判決以上に自己に不利益な判決がなされないという保障が与えられることになります。
その根拠は、控訴審における処分権主義、すなわち、控訴審において不服申立てに関する主張を当事者の責任かつ権能とする建前のことです。さらに、原判決により控訴人が受けた不利益を救済するために設けられたものであることもあげられます。
※当事者の主張や処分権主義との関係については、関連記事「裁判上の自白について」も参考になります。
[事例]と似たような場面について判断を示した判例の立場は次のようなものになります(最判昭和58年3月22日集民138号315頁)。
原審は予備的請求についてのみ認められ、主位的請求は認められていないが、控訴審では、主位的請求が認められているから、原審と比較すると不利益である。そうすると、上述の不利益変更禁止の原則により、主位的請求については、審判範囲に含まれていないことになります。
※訴訟物の把握や請求構造の整理については、関連記事「所有権に基づく不動産明渡請求訴訟の請求の趣旨と訴訟物について」も参考になります。
このような考え方に対して、学説上は、主位的請求についても審判対象になると考える立場も主張されています。この立場は、予備的併合のときは両請求が密接な関係にあるから、統一的な解決を図る必要があるから、主位的請求について審判対象になると考えています。
このような学説に対して、判例の立場をとる学説からは次のように批判されています。
主位的請求棄却の部分に対して原告は控訴も附帯控訴もしていないから不服の意思を表明していないにもかかわらず、反対説の立場は、主位的請求も審判対象になってしまいます。そうすると、主位的請求部分について、第1審判決が請求棄却判決であるにもかかわらず、認容判決になる可能性があり、このような判決は、控訴人である第1審被告にとって不利益な判決になってしまいます。以上のような、判例の立場を採用すべきです。
なお、判例の立場を採用する場合であっても、控訴審裁判所は、原告の意思を確認するために釈明権を行使すべきです。そこで、釈明権の不行使により違法になるかは別途検討の必要があります。
※控訴審における主張立証や証拠の取扱いについては、関連記事「民事訴訟の場面において証拠となる文書はどのように提出しますか」や「文書提出命令が発令される要件について」も参考になります。
[事例]の場合には、控訴審の審判範囲は主位的請求に含まれていないから、控訴審が主位的請求を認容する判決をすることができません。
したがって、予備的請求認容部分を棄却するにとどめる必要があり、控訴審裁判所は、第1審判決のうち、予備的請求認容判決の部分を取消す必要があります。
以上から、控訴審裁判所は、原判決のうち、予備的請求認容の部分を取り消すとともに、原告の予備的請求を棄却する自判をすべきことになります。

控訴審で、どのような主張をすべきかの詳細につきましては、弁護士までお問い合わせください。