
-
よい ゴール0120-410-506
- お問い合わせフォーム
よい ゴール0120-410-506
今回は、強制捜査と任意捜査の区別について解説させていただきます。

強制捜査とは、「強制の処分」(刑事訴訟法197条1項ただし書)を用いる捜査のことを言います。
強制捜査に該当する場合には、強制処分法定主義や令状主義の規律を受けることになります。そこで、これらの用語について解説していきます。
強制処分法定主義とは、刑事訴訟法上に特別の根拠規定がなければ強制の処分を行うことができないという考え方になります。根拠となる条文は、刑事訴訟法197条1項ただし書です。
国民の権利利益を侵害するような捜査について、いかなる内容・形態の処分をどのような要件・手続で認めるかは、国民の代表である国会が制定した法律で規律することによって、国民の自由を担保しようという考え方が強制処分法定主義を採用した根拠になります。
そして、このような根拠を踏まえると、捜査を担当する捜査機関だけでなく、司法権を担う裁判所も強制処分法定主義に従う必要があります。その結果、裁判所が法の解釈により法定された強制処分以外の強制処分を適法な捜査として採用すべきだという判断をすることは刑事訴訟法197条1項ただし書に反することになります。
令状主義とは、捜査機関が個別具体的な事案において強制の処分を行うためには、原則として、裁判官が強制の処分を行う正当な理由と必要性について事前審査を行って発付する令状が要求されるという考え方です。
重大な権利侵害を伴う強制の処分を行うことができるか否かを、事案の解明を目的として捜査を行う捜査機関に委ねてしまうことは危険であると考えられることから、捜査機関に強制の処分を行う裁量を与えない必要があります。
そこで、捜査機関から中立した立場にある裁判官が、強制の処分を行う正当な理由と必要性の有無について事前に審査することで、不当な権利侵害が起きることを防ぐために令状主義が採用されました。
なお、この令状主義は、強制の処分に該当するあらゆる場面で適用されるわけではありません。例えば、現行犯逮捕の場合や逮捕に伴う無令状捜索差押えの場合のように、強制の処分を行う正当な理由や必要性が捜査機関にとって明らかな場合には、裁判官の事前の審査を行う必要がないことから令状が要求されません。
任意捜査とは、強制捜査以外の捜査のことを言います。刑事訴訟法には、任意捜査に関する規律はあまり置かれていません。任意捜査に該当する場合には、捜査機関が自身の裁量で捜査を行うことができます。
任意捜査であっても、何らかの権利侵害を伴うこともあり得ます。そこで、任意捜査は、その目的を達するため必要な限度で認められています。
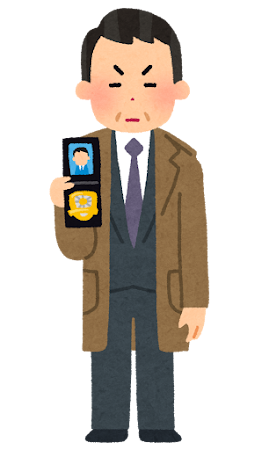
以上で見てきたように、強制捜査に該当する場合と任意捜査に該当する場合とで適用される法的規律が異なります。そうすると、捜査が適法であるか違法であるかを判断する枠組みが異なることにもなります。
そこで、捜査が適法であるか違法であるかを判断する枠組みについて、判例の立場などについて説明をさせていただきます
強制の処分は、捜査機関による有形力の行使を伴うような処分を意味するという立場がありました。
しかし、このような立場に対しては、2つの批判があります。
まず、1つ目の批判としては、有形力の行使にもさまざまな形態があります。軽微な有形力の行使についてまで強制処分に該当すると考えてしまうと、さまざまな捜査に令状が必要となってしまいます。したがって、有形力の行使の中でも制限させる必要があります。
2つ目の批判としては、強制の処分を有形力の行使だと考えてしまうと、有形力の行使を伴わない権利侵害の類型には令状が必要ないということになってしまいます。
例えば、通信の秘密は、憲法21条2項後段で保護された権利です。捜査機関が、通信傍受を行った場合、有形力行使説によると、有形力の行使を伴わないことから、通信の秘密という重要な権利利益の侵害があるにもかかわらず、捜査機関は令状なく通信傍受を行えることになってしまいます。
以上のような批判があることから、有形力の行使と考えるべきではないといえるでしょう。
以上のような、有形力の行使説を批判して、判例は強制の処分を次のように定義しました。
すなわち、強制の処分とは、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するもの」(最判昭和51年3月16日刑集30巻2号187頁)だという立場です。
このうち、強制的に捜査目的を実現する行為は、強制処分の言い換えだといえるでしょう。また、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものとは、刑事訴訟法197条1項ただし書の効果を示しているものです。
以上のようなことを踏まえると、個人の意思を制圧するという部分と重要な法的利益を侵害するという部分の2つが重要になります。
以上から、強制処分の定義は、「個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するもの」(最判平成29年3月15日刑集71巻3号13頁)だといえるでしょう。

以上のように、強制の処分は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するような処分です。このような処分にあたる場合、強制処分法定主義違反または令状主義違反になれば捜査が違法になります。
そして、この定義にあてはまらない捜査が任意捜査になります。
捜査機関による違法捜査に当たるか否かでお困りの方は、詳しくは弁護士までお問い合わせください。
