
-
よい ゴール0120-410-506
- お問い合わせフォーム
よい ゴール0120-410-506
今回は、名誉毀損罪がどのような場合に成立するのかについてご紹介させていただきます。

刑法230条1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と定めています。
刑法は、法益を保護するための法律です。それでは、名誉毀損罪は、どのような法益を保護するために設けられているのでしょうか。まずは、その点についてご紹介させていただきます。
刑法の名誉毀損罪は、個人の名誉を守るために設けられています。
それでは、この名誉とはどのような概念でしょうか。
名誉は、内部的名誉、外部的名誉、名誉感情の3種類に分かれると考えられています。
内部的名誉とは、人の人格的価値そのもののことです。
外部的名誉とは、人の人格的価値に対する社会的評価のことです。
名誉感情とは、人の人格的価値に対する自己評価の意識のことです。
これら3つの名誉の概念のうち、名誉毀損罪は、外部的名誉を保護するために設けられているものだと考えられています。
内部的名誉は、外部から侵害されるものではないことから、法律で保護する必要はありません。また、名誉毀損罪は、刑法230条の条文を見ればわかるように、具体的な事実を摘示することで成立するものです。これは、人の社会的評価を下げるようなものです。このような理由から、名誉毀損罪は、外部的名誉を保護するために設けられたものだといえるでしょう。
また、刑法230条は、名誉毀損罪が、摘示された事実の有無にかかわらず処罰の対象になると定めています。これは、この外部的名誉のうち、事実的名誉、すなわち、社会で現実に通用している評価を保護するものとしていることをあらわしているといえるでしょう。
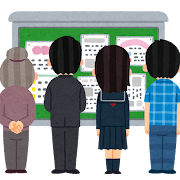
以上のように、名誉毀損罪は、人の社会で現実に通用している評価を保護するために設けられたものです。それでは、名誉毀損罪の成立要件はどうなっているのでしょうか。次に、この点についてご紹介させていただきます。
まず、「公然」という言葉の意味を紹介させていただきます。
公然とは、不特定または多数の人が知りうる状態のことを意味しています(最判昭和34年5月7日刑集13巻5号641頁)。
この公然の定義からすると、例えば、特定かつ少数人が知りうる状態で事実の摘示をしたとしても名誉毀損罪は成立しないことになります。
以上のように、名誉毀損罪が成立しなくなる特定かつ少数人が知りうる状態で事実の摘示をした場合であっても、その事実を聞いた特定かつ少数の人から多数人に事実が伝達された結果、社会で現実に通用している評価が低下するという結果がもたらされてしまう可能性があります。
そこで、判例法理上、直接事実の伝達を受けた者が特定かつ少数人であったとしても、その者を通じて不特定多数人に伝わる可能性が認められる場合には、公然性が認められるとしています(大判大正8年4月18日新聞1556号25頁)。
このような考え方を「伝播性の理論」といいます。
次に、摘示される事実はどのような事実である必要があるかを紹介します。
名誉毀損罪は、人の社会的評価が低下することを防ぐために設けられた犯罪です。この保護法益を踏まえると、摘示される事実は、人の社会的評価を低下させるような具体的な事実である必要があります。
一方で、摘示された事実が具体的な事実ではない場合には、同じく人の外部的名誉を保護するために設けられたものであると考えられる侮辱罪が成立することになります。
死者の名誉を毀損した場合には、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、名誉毀損罪は成立しません(刑法230条2項)。
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損した場合に成立します。それでは、この「名誉を毀損」するとはどのような意味でしょうか。
判例によると、名誉毀損罪は、抽象的危険犯とされています。この抽象的危険犯は、法益が侵害されるおそれが発生していれば足り、具体的に法益侵害の結果が発生する必要はないとしています(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)。
なぜならば、現実に社会的評価が低下したことを立証することは困難だからです。また、仮に立証できるとしても、立証の際に被害者をさらに傷つける結果となるおそれがあります。
以上のような理由から、人の社会的評価を低下させるに足りる事実が不特定または多数人に対して摘示された場合には、それだけで直ちに名誉毀損罪が成立すると考えられています。

以上でみてきたように、名誉毀損罪は、人の社会的評価を低下させるに足りる事実が不特定または多数人に対して摘示することで成立する犯罪です。ただし、刑法230条の2が適用される場合には、処罰を免れます。
名誉毀損罪に関する具体的な刑事事件においてお困りの方は弁護士までお問い合わせください。
