
-
よい ゴール0120-410-506
- お問い合わせフォーム
よい ゴール0120-410-506
今回は、刑事訴訟における証拠法の考え方の1つである伝聞法則について紹介させていただきます。
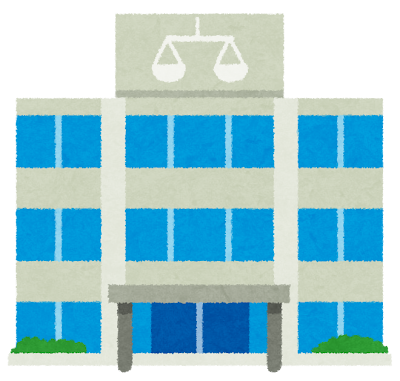
人の供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の各過程を経て生成される。この各過程には誤りが入りやすいです。そこで、公判廷で、宣誓と偽証罪による警告のもと、反対尋問を経て生成された供述を事実認定者が直接観察することで、信用性を吟味する機会が必要です。
しかし、公判廷外での人の供述には、そのような機会が用意されていないから、事実認定者が判断を誤る危険性があります。
そこで、公判廷外での人の供述を内容とする人の供述または書面の証拠能力を原則として認めないこととしました。このような考え方を伝聞法則といいます。
伝聞法則の適用される伝聞証拠に当たる要件は以下の2つになります。
①公判廷外の人の供述を内容とする人の供述または書面
②その供述内容通りの事実があったことを証明するために用いる場合
伝聞証拠に該当した場合には、刑事訴訟法321条以下にある伝聞例外の要件を充たさない限りは、証拠能力が認められないことになります。

次に、「その供述内容通りの事実があったことを証明するために用いる場合」という伝聞証拠の要件を理解するために、事実認定の構造を理解していきましょう。
刑事訴訟における事実認定の方法には以下の2つのパターンがあります。
・直接証拠から証明する場合
・間接事実から推認する場合
〔図〕
構成要件に該当する具体的事実 ← 証明 ← 直接証拠
↑
推認
↑
間接事実
↑
証明
↑
間接証拠
次に、理解の前提となる証拠法における用語を説明しておきます。
物証は、例えば、ナイフのような物を証拠とする場合に用いる用語です。これに対して、供述証拠とは、供述内容通りの事実があることを示すために用いる証拠のことです。
・供述証拠の概念
ここでは、供述証拠がどのようなものかを理解するために、以下の事例を用いましょう。
まず、「AとBが手をつないでいるのを見た」という旨のXの供述があったときには、どんな事実を示せるでしょうか。「AとBが手をつないでいた」という事実が明らかになると思います。
供述が書面に書かれている場合も同様です。「AとBが手をつないでいた」と書いてあるXの日記から明らかになる事実も「AとBが手をつないでいた」という事実です。
このように、供述証拠から、ある事実があったことを証明することができます。このような場面のことを指して、供述内容通りの事実があったことを示す場合という言葉を用いています。
・推認の考え方
「AとBが同じ指輪をしていた」というXの供述からは、「AとBが同じ指輪をしているという事実」が直接には証明できます。
しかし、この事実から別の事実を推認することもできます。推認とは、ある事実の存在を、経験則に従って他の事実から導き出すことを意味しています。
例えば、AとBが同じ指輪をしているという事実から、AとBが恋人関係にあるという事実を「推認」できます。この推認は、カップルでない限り普通は同じ指輪をつけないという経験則によるものです。
・その供述内容通りの事実があったことを示す場合とは?(内容の真実性とは)
公判期日の証人尋問において「AとBが同じ指輪をしていた」とXが供述したという事例を用いてみると、Xの供述は、「AとBが同じ指輪をしていた」という内容です。そして、「AとBが同じ指輪をしていた」というXの供述から「AとBが同じ指輪をしていた」というXの供述の内容通りの事実があったことを証明するために用いています。したがって、その供述内容通りの事実があったことを示す場合に当たると言えます。

伝聞証拠に当たるか否かは、どのような事実を要証事実により定めるかにより決まると言われています。それは、次のような理由です。
例えば、「「AとBが同じ指輪をしていた」とXが言っていたのを聞いた」というYの供述からどのような事実が証明できるでしょうか。
まず、「AとBが同じ指輪をしていた」という事実が考えられます。次に、「「AとBが同じ指輪をしていた」とXが言っていた」という事実も考えられます。
これら2つの事実は別の事実であることは明らかです。このうち、「AとBが同じ指輪をしていた」という事実を導きだすためには、Yの供述の内容になっているXの発言の内容通りの事実があったか否かを示す必要があります。このような場面において、裁判官が話を聞くべきは、YではなくXです。Xがどのような状況で見たのかについて聞いておくことで誤った判断を避けることができるでしょう。したがって、伝聞証拠に当たります。
一方で、「Xが言っていた」か否かが重要な事実になっているときには、Yが聞いた状況が大事になります。そうすると、Yを尋問すれば誤った判断を避けるためには十分であり、Xから話を聞く必要はないといえるでしょう。
このように、同じ人の供述でも、何を証明の対象となる事実とするかにより、伝聞にすべきかどうかは変わってきます。したがって、要証事実が何であるかによって伝聞証拠か否かが決まります。
以上のような伝聞証拠の考え方は、刑事訴訟上きわめて重要なものです。
具体的な事件において、特定の証拠が伝聞証拠に当たるか否かは、要証事実が何であるかによって変化します。
具体的な刑事事件についてお困りの方は弁護士までお問い合わせください。
