
-
よい ゴール0120-410-506
- お問い合わせフォーム
よい ゴール0120-410-506
今回は、名誉毀損罪の処罰を免れることができる場合がどのような場合であるかについてご紹介させていただきます。
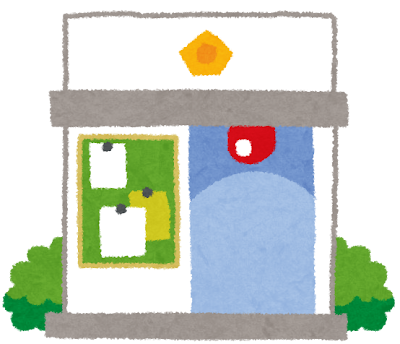
名誉毀損罪は、人の外部的名誉、すなわち、人の社会的評価を保護するために設けられた犯罪です。具体的には、人の社会的評価を低下させるに足りる事実が不特定または多数人に対して摘示することで成立します。
名誉毀損罪の成立要件についての詳細は、こちらをご覧ください。

名誉毀損罪が成立したとしても、処罰を免れることができる場合があります。それが、刑法230条の2の場合、すなわち、公共の利害に関する特例の場合です。
刑法230条の2は、「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」としています。
この条文における前条第1項の行為とは、名誉毀損罪が成立する行為を意味しています。
それでは、刑法230条の2はどのような趣旨・目的で設けられた規定なのでしょうか。まずは、その点から紹介させていただきます。
刑法230条の2は、1947年に新たに追加されたものです。同条は、名誉の保護と表現の自由との調整を図るために設けられた規定になります。
刑法230条の2が「これを罰しない」としている意味については学説上対立があります。処罰が阻却される事由を定めたものだとする処罰阻却自由説が立案担当者の考え方でした。しかし、この処罰阻却事由説によると、表現の自由を行使することが違法な行為だと評価してしまうことになります。このように憲法上認められた基本的人権であるはずの表現の自由行使を違法な行為だと評価するのは適切ではないという批判が多くありました。
そこで、名誉毀損罪に当たる行為がされたとしても、公共の利害に関する場合には、違法性が阻却されるとする違法性阻却事由説が現在の通説的な考え方です。
それでは、公共の利害に関する特例は、どのような場合に認められるのでしょうか。
刑法230条の2によると、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき」に違法性が阻却されるとしています。
この条文の文言から、①公共の利害に関する事実に係ること(事実の公共性)、②目的が専ら公益を図ることにあること(目的の公益性)、③摘示された事実が真実であることの証明があること(真実性の証明)という3つの事実が認められる必要があります。
以下では、これら3つの要件の意味をそれぞれ明らかにしていきます。
まずは、「公共の利害に関する事実」とはどのような意味かをご紹介させていただきます。
「公共の利害に関する事実」とは、一般多数人の利益に係る事実のことです。
男女関係のような私生活上の事実であっても、公共の事柄に関する評価の資料になる事実は、公共の利害に関する事実に当たるとした判例があります(最判昭和56年4月15日刑集35巻3号84頁)。
なお、刑法230条の2第2項には、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなすという規定が設けられています。
刑法230条の2の文言は、「目的が専ら公益を図ることにあること」とあります。しかし、主たる動機が公益を図ることにあれば足りるとするのが裁判例の考え方です。
判例は、目的の公益性を判断するに当たっては、摘示方法の適切さなどの客観的な事情を考慮すべきであるとしています。
最後の要件が、摘示された事実が真実であると証明されることです。
「証明」という文言から、被告人側で摘示された事実が真実であったことを積極的に証明する必要があります。したがって、摘示された事実があったか否か真偽不明の状態に陥った場合には、刑法230条の2は適用されず、名誉毀損罪が成立することになります。
噂や風評の形で事実が摘示されている場合には、そのような噂や風評の内容になっている事実の存在が真実性の証明の対象になります(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。噂や風評の内容となっている事実が被害者の社会的な評価を低下させるものであることがその理由です。
なお、真実性について誤信していた場合にも、名誉毀損罪は成立しないとする判例があります(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。
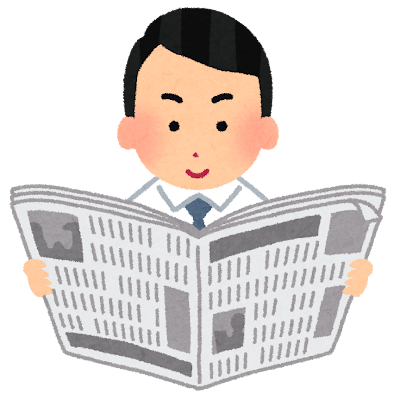
以上でみてきたように、名誉毀損罪が成立する場合でも、①事実の公共性、②目的の公益性が認められ、③真実性の証明があった場合には、違法性が阻却される結果、処罰を免れることができます。
具体的な刑事事件において、名誉毀損罪の処罰を免れることができるかは、弁護士までお問い合わせください。
