
-
よい ゴール0120-410-506
- お問い合わせフォーム
よい ゴール0120-410-506
皆さんは、刑事裁判の法廷で検察官が証人尋問を行う中、弁護士が「異議あり!」と声を上げるシーンをドラマやアニメ、ゲームなどで目にしたことがあるのではないでしょうか。この「異議あり」という言葉は、単なる演出ではなく、法律に基づいて発せられる重要な発言です。
この記事では、刑事裁判の法廷において、どのような場面で弁護士が「異議あり」と述べることができるのかを、法律の規定とともにわかりやすく解説します。
関連コラム
強制捜査と任意捜査の区別について
伝聞法則とは何か
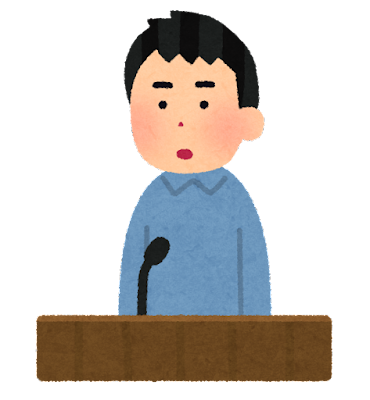
「異議あり」には大きく2つの意味があります。1つ目は、証拠意見としての異議です。
刑事裁判で提出される証拠は、すべてが自動的に採用されるわけではありません。裁判所が「証拠決定」を行い、採用するかどうかを決めます(刑事訴訟規則190条2項)。
検察官が証拠調べ請求を行うと、被告人または弁護人に意見を述べる機会が与えられます。証拠が書面の場合は「同意」「不同意」と意見を述べますが、物証や証人尋問の場合は、「異議なし」「異議あり」という意見表明がなされます。
このように、証拠採否に関する意思表示としての「異議あり」が、証拠意見としての異議なのです。
関連コラム
裁判上の自白について

もう一つの「異議あり」は、皆さんがドラマなどでよく目にする場面です。これは、法令違反や不相当を理由とする異議です。
刑事訴訟法309条では、検察官、被告人、弁護人が、裁判長の処分や証拠調べに対して異議を申し立てることが認められています。刑事訴訟規則205条では、証拠調べの決定や裁判長の処分に対しては、法令違反のみを理由に異議を申し立てることが定められています。
しかし、証拠調べの決定以外の証拠調べに対する異議は、法令違反だけでなく「不相当」という理由でも異議を申し立てることができます。
この異議は、違法・不相当な行為を正すとともに、裁判員も含む裁判所が不適切な情報を知ることを防ぐ目的があります。そのため、法廷で弁護士が「異議あり」と述べるのは、ただの発言ではなく法律に基づく正当な行為です(刑事訴訟規則205条の4)。
関連コラム
保釈について
勾留に対する法的な対応について
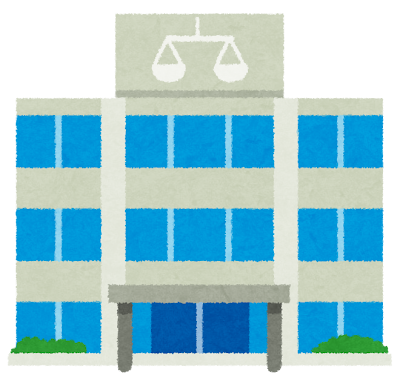
証人尋問には「主尋問」と「反対尋問」があります(刑事訴訟規則199条の2第1項1号)。主尋問では、基本的に誘導尋問が禁止されています(刑事訴訟規則199条の3)。
誘導尋問とは、質問者が特定の答えを期待・暗示する質問のことで、例えば「あなたは右手で殴られたのですか?」といった質問が該当します。
ただし、証人の経歴などの準備的な事項や争いのない事実に関しては例外的に認められる場合もあります。検察官の主尋問で誘導尋問が行われた場合、弁護士は「異議あり」と述べます。
関連コラム
伝聞法則とは何か
反対尋問は、主尋問後に行われ、以下の範囲内で質問が許されます(刑事訴訟規則199条の4第1項):
1.主尋問に現れた事項
2.上記に関連する事項
3.証人の供述の信用性を争うために必要な事項
それ以外を尋問する場合は、裁判長の許可が必要です(刑事訴訟規則199条の5)。もし検察官が許可なく別の事項を尋ねた場合、弁護士は「異議あり」と述べます。
誤導尋問とは、質問の前提が間違っていたり、証言内容を不適切に要約する質問のことです。
例として:
・実際にはコンビニに行っていないのに「コンビニに行ったとき被害者を見ましたか?」と尋ねる
・「何かを振り上げた」としか言っていないのに「刃物を振り上げた後どうしましたか?」と尋ねる
このような誤導尋問にも、弁護士は「異議あり」と述べて阻止します。
刑事訴訟規則では、すべての尋問で許されない方法を明示しています。
・威嚇的な尋問
・侮辱的な尋問
また、以下の尋問は例外的に許される場合を除き、原則禁止です:
・重複する尋問
・意見や議論を求める尋問
・証人が直接経験していない事実の尋問

刑事裁判で弁護士が「異議あり」と述べるのは、法律で定められた正当な権利であり、裁判の公正を守るために欠かせない行為です。それ以外の場面で「異議あり」と述べることは許されません。
実際の法廷を傍聴することで、こうした「異議あり」の瞬間を目にし、より深く理解することができます。ぜひ興味があれば傍聴に足を運んでみてください。
